梅酒特区・みなべ町から生まれた、世界初のクラフトジン梅酒「Yii」


みなべクラフト梅酒の「Yii(イー)」について、おすすめポイントを紹介しよう。
南高梅の生産日本一を誇るみなべ町の農家がつくる梅酒
地場産の梅を原料にした梅酒であれば、少量の年間生産量でも酒類製造免許を受けることができる「紀州みなべ梅酒特区」に認定されている和歌山県・みなべ町。そんな梅の産地で、梅を知り尽くした農家が自ら仕込む特別な梅酒だ。
一粒一粒手摘みした、木熟の南高梅を贅沢に使う
芳醇な香りがあり、果汁の多い南高梅は梅酒に最適。また木から落ちる寸前の「木熟」という一番良い状態のものだけを手で収穫して使っているので、風味が段違いに良い。
世界で初めてベースにジンを使った他にない味わい
一般的な梅酒のベースは無味無臭のホワイトリカーを使用する。しかし「Yii」にはウッディなジュニパーベリーが香るジンを使い、甘味を抑えることで、常温ストレートでも美味しい梅酒に仕上げている。
南高梅農家がつくった梅酒との出会い
2008年に「紀州みなべ梅酒特区」に認定されたみなべ町では、小規模の梅酒メーカーが多数存在する。通常、酒造製造免許を取得するためには、最低でも年間6000リットルの酒類を製造しなければならないが、みなべ町では地場産の梅を原料とし町内で梅酒を製造する場合、最低年間1000リットルの製造量で免許を受けることができる。梅酒の作り手が増えたことで、個性豊かな梅酒が生みだされる地域になった。
梅酒といえば、甘くて飲みやすい果実酒の代表格。そんな梅酒の概念を変えたのが、「Yii(イー)」。全国に流通する南高梅の約25%の生産量を誇る和歌山県みなべ町で、梅農家自らが仕込むクラフト梅酒だ。
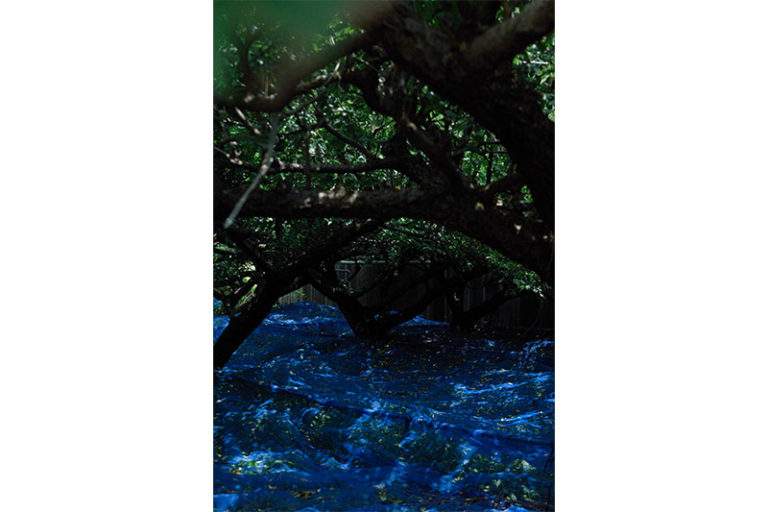
「Yii」の製造販売を行う高田遼さんが、みなべ町の梅酒を知ったのは6年ほど前のこと。みなべ町出身の高田さんの祖父母は60年続く梅農家。小さな頃から毎年6月は収穫の手伝いに駆り出され、梅の加工品は身近な存在であった。とはいえ、大人になった高田さんが好んだ酒類はワインやウイスキー。梅酒にはほとんど興味がなかった高田さんに、人生を変える出会いが訪れる。

「まちの梅まつりで農家さんが作った梅酒を見つけて、何気なく飲んだんです。そしたら、香りも味も市販のものとは全く違って感動してしまって。それと同時に、こんなに美味しいのにブランディングがいまいちだったりして、もったいないなと思いました」。
高田さんの転機となったのは祖父母の引退。母親が畑を引き継ぐことになり、そのタイミングで自身も梅酒ブランドを立ち上げようと考えた
ジンを使ったクラフト梅酒の先駆者
目指したのは、作り手や土地の風土が透けて見えるような梅酒。高田さんはすでにまちで作られていたいくつかの梅酒を「みなべクラフト梅酒」としてブランド化。さらにオリジナルの梅酒づくりにも着手した。ベースのスピリッツに選んだのは、これまで前例のなかったジンだ。

「僕もジンが好きでしたし、調べてみると当時まだ誰もやっていなかったので、ジンを使った梅酒作りに挑戦しました。国内外から集めた約20種類のジンと、黒糖や蜂蜜などいろんな砂糖を合わせて、何十通りもジン梅酒を仕込みました。1種類が完成するまでに半年間漬け込まなくてはいけないので、納得のいく味のものが完成するまで2年半くらいかかりましたね」。
最終的に選んだのは、偶然にも同じ和歌山県産の「榊ジン」。ボタニカルに梅が入っていて、ジュニパーベリーのウッディな香りもしっかりしている。砂糖は自然な甘味のてんさい糖で、量を一般的な梅酒の3分の1ほどに調整。「Yii」という商品名は、“これがクラフト梅酒だ!”という意味を込めた「Yes it is.」の略になっている。

「南高梅を贅沢に使えるのは梅農家の特権。また、梅は木から落ちる寸前の木熟状態が、一番香りが良いと言われているので、『Yii』に使う梅は母と僕で一つひとつ見極めて、手で収穫しています。この一本がクラフト梅酒の第一歩。アイコン的な存在になってくれたら」。

おすすめの飲み方は常温ストレート。甘さを抑えているので冷やす必要がなく、常温のほうが芳醇な香りが広がりやすい。また食中酒としても優秀で、肉料理との相性は抜群。飲んでみると梅の上品な果実味とスパイシーなボタニカルのバランスが絶妙で、口の中でじっくりと楽しみたくなる。

また「Yii」を含む5種類のミニボトルのセットも販売している。いろいろな味わいを楽しみたい方にはこちらもおすすめだ。

2021年に「Yii」をリリースしてから、高田さんはじっくりと時間をかけてブランドを育ててきた。イベント出店や飲食店でのテイスティングには自ら赴き、飲み手と直接コミュニケーションを取ることにこだわる。丁寧なものづくりとストーリーテリングが実を結び、2024年9月に開催されたICC SAKE AWARDでは予選1位通過、最終4位という快挙を達成。アワード史上初となる4部門賞(美味しさ、ブランディング、製法へのこだわり、想いへの共感)を制覇した。今後は海外でも展開していくという。

「普段梅酒を飲まない方がイベントでボトルを購入してくださって、クラフト梅酒の魅力が伝わっているのを肌で感じています」。
「今後は『Yii』を使ったカクテルを開発するなど、飲み手の幅を広げていきたいです。クラフト梅酒という新しいジャンルのアイコンとなれるようなブランドに育てていきたいです」。
今後は海外への販売も始め、世界にみなべの南高梅の魅力をさらに発信していきたい、と高田さんは語る。今までにないクラフト梅酒という新しいジャンル。お酒好きの人の好奇心をそそる贈り物になるのではないだろうか。









