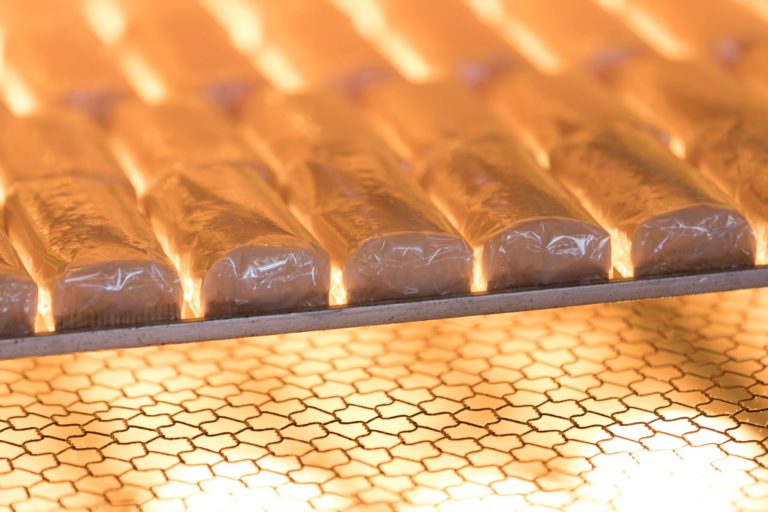過酷な気候でこそ生育する 不老長寿の実「ハスカップ」

そのなかでも、最近の健康ブームも手伝って注目されているのが「ハスカップ」。認知度が高まりつつあるハスカップだが、実物を見たことのある人はそれほど多くないだろう。それもそのはず、国内でハスカップが自生するのは本州のごく一部の地域と北海道だけ。国内に流通するハスカップのほとんどを道内の生産者が担っているのだ。
アイヌに伝わる不老長寿の実

ハスカップは、古来よりアイヌ民族の間で「不老長寿の実」として伝えられてきた。最近は少なくなってきているが、古くは道内の各地に群生していたという。
ハスカップの原産はシベリアとされており、渡り鳥が北海道の原野に種を運んできたというのが地元生産者の定説だ。そんな出自もあってか、ハスカップには特殊な生育条件がある。その条件とは、冬の期間がマイナス20℃以下、さらに夏の間は30℃以上にならないこと。冷涼な北海道だからこそ、ハスカップはすくすくと育ち、あちこちに根づいていった。
また、北海道の地質もハスカップ栽培に大きく関係している。全国の湿地面積のおよそ8割を北海道が占めており、湿地のなかには枯れた植物などの有機質が堆積した泥炭地も少なくない。
地盤のゆるい泥炭地は農業には不向きのため、北海道開拓者は大規模な土地改良を余儀なくされるわけだが、根が浅く広がるハスカップは泥炭地でもよく育つという。実際、勇払原野をはじめ釧路湿原、霧多布湿原などの湿地が自生地になっている。
ハスカップといえば、独特の酸味と苦味が特徴。あの味覚は抗酸化作用のあるポリフェノールの一種、アントシアニンによるものだ。アントシアニン含有量は、ブルーベリーの3倍から10倍ともいわれている。そのほか、カルシウムはリンゴの13倍、鉄はミカンの6倍、そのほかビタミンC、ミネラルも豊富。「不老長寿の実」の表現も、決して大げさではないのだ。
産地の個性が現れる、ハスカップ

7月半ば、日高山脈をのぞむ帯広市岩内町の「ときいろファーム」を訪ねた。大規模で機械化された農業が一般的な帯広において、ときいろファームではラズベリーやブルーベリー、ハスカップなどの小果樹を栽培している。
高さ1~2mほどの落葉低木であるハスカップは、地面から直接生えるように枝が旺盛に伸びる。5月中旬から小さな黄色い花が咲き始め、やがて花から果実が実る。みどり色の果実は成熟が進むにつれて着色が進み、7月の収穫期には青黒い果実になる。農園を訪れた日は、ちょうど収穫期。スタッフたちが果実を丁寧な手つきで収穫していた。
「ラズベリーほどではありませんが、ハスカップも傷がつきやすく傷みやすい。そのため機械化はむずかしく、収穫は人の手に頼るしかないんです」。

迎えてくれたのは、農園を経営する鴇崎伊吹(ときざきいぶき)さん。もともと長野県出身の鴇崎さんだが、妻の姿名子(しなこ)さんと結婚後、自転車とバックパックをかついでヨーロッパ11カ国を夫妻で放浪。帰国後、宿泊業に携わったのち北海道に移住し、2010年に就農した。就農2年目から、ハスカップの本格的な栽培に取り組んでいる。
「ハスカップの栽培面積は2.5ヘクタールほど。この農園の果樹は、有機JAS規格に基づいた無農薬、無化学肥料で栽培しています。化学肥料を否定するわけではありませんが、自然に近い環境が本来の美味しさをひき出せる気がするんです」。
種々の草木に囲まれたハスカップは、力強く枝葉を広げ、鈴なりに果実を実らせている。鴇崎さんに促されて果実を一粒口にふくむと、ほのかな甘みとともに、力強さのある酸味と苦味が口いっぱいにひろがった。野趣あふれる味わいに、一粒、二粒…と手がとまらなくなってしまう。

「ハスカップはその土地の水や土壌に影響を受けやすいんです。おもしろいもので、同じ農園内でも植えられている場所によって味が微妙に違うことも。生産者の主義やこだわりが現れやすい、ともいえますね」。
ときいろファームでは、一般客に対してハスカップの収穫体験に応じている。農園に足を運び、自らの手で摘んで食べる。北海道ならではの贅沢な体験だ。生では食べられない本州や離島の人には、鴇崎さんはハスカップのジャムやソースをすすめている。あの独特の風味がヨーグルトなどの乳製品によく合うそうだ。
時代をつなぐ生産者たちの挑戦

夏が過ぎ収穫が落ちつくころ、鴇崎さんの全国行脚の旅が始まる。目的はハスカップをはじめベリー類を使ったスムージーや、冷凍ベリー、ジャム、ジュースなどの加工品の販売。スムージーはハスカップなどのベリー類、てんさい糖、水でつくられる。素材の味を引き立てるため、極力手を加えずに最小限の材料にこだわった。
「9、10、11月は、全国各地を巡ります。道内はもちろん、東京、奈良、横浜などを奔走。ハスカップを知ってもらうきっかけにもなる。もちろん、全国を回るのは大変です。けど、お客さまの笑顔を見るのがなによりも嬉しい」
鴇崎さんのような生産者がいる一方で、ハスカップ栽培には大きな課題がある。道内のハスカップの栽培面積は1991年をピークに、2003年には半分以下にまで減少している。生産量が急増した結果、需要と供給のバランスがくずれ、単価は急落。その結果、多くの農家がハスカップ栽培から撤退した。そのしわ寄せから、いまだハスカップの安定供給には至っていない。鴇崎さんはこの現状をどう見ているのか。
「小規模の農家でトン単位を供給するのは難しい。やはり、生産者同士で連携していかなくてはいけません。実際、そういった兆しも見えてきました。情報共有したり、協力して販路拡大をしたり。いまがハスカップ生産者にとって大事な時期といえるでしょう」。
北海道に根づいたハスカップが新たに迎えた局面。その未来は、ときいろファームをはじめとする気鋭の生産者たちにゆだねられている。
ハスカップ
情報提供:ときいろファーム 鴇崎伊吹さん
“旬”の時期
7月上旬~8月上旬
目利きポイント
実がふっくらと、青黒く熟れて、表面が白く覆われているもの
美味しい食べ方
生で冷やしてヨーグルトに入れたり、残ったものは冷凍してそのまま食べるのがおすすめ。