日本の風土や文化に育まれ、発展を続ける「羊羹」

今回は、虎屋にある菓子資料室、虎屋文庫で、研究主査を務める森田環さんに、もともと中国の料理だった羊羹が日本にもたらされ、菓子としてつくられるようになったという歴史や、特色ある各地の羊羹など、奥が深い羊羹の世界についてお伺いした。
中国の羊の汁物「羊羹」が、菓子として独自に進化

「羊羹は、紀元前から中国で食べられていた料理が原形です。『羹』というのが汁物を指すので、文字通り、羊肉入りの汁物のことで、とても贅沢なごちそうだったようです」と、森田さんは語る。
日本に羊羹が伝わったのは、鎌倉~室町時代(12世紀末~16世紀後半)のことで、中国に留学していた禅僧によって、点心(てんじん)の食習慣とともにもたらされた。当時の食事は朝と晩の2回のみだったが、その間に食べる軽食のことを点心といい、その中に羊羹も含まれていた。

「日本に羊羹が伝わった際は、中国と同じように料理だったと思われます。ただ、禅僧は肉食が禁じられていたため、小豆や小麦粉など植物性の原材料を使い羊の肉に見立てていたと考えられます。残念ながら当時のレシピは残っていませんが、この肉に見立てた食べ物がのちに蒸羊羹の原形になっていったと思われます」。
はじめは寺院で食べられていた羊羹だが、次第に貴族や武家の間にも広がっていった。舶来品の羊羹は格式のある食べ物とみなされ、貴族の饗応料理をモデルに武家が形式にのっとって客人をもてなす本膳料理の一つとして扱われるようになっていった。

室町時代後期の武家の作法書『食物服用之巻(しょくもつふくようのまき)』(1504年頃)に、羊羹の図がみられる。ここでは、薬味や梅干しなどと一緒にお膳に載っており、汁は別に用意されていた。
「戦国時代には、御成(おなり)と称し、主君が臣下の屋敷を訪れて、もてなしをうける儀礼が盛んに行われるのですが、その饗応の献立のなかに羊羹がありました。記録を見ると、はじめのうちは酒の肴として出されているのですが、のちには菓子としても供されていたことがわかります」。
菓子としての羊羹の進化

江戸時代に入ると、料理としての羊羹はほぼ姿を消し、菓子として扱われるようになる。ポルトガル語による日本語の辞書『日葡辞書(にっぽじしょ)』(1603年)に、「羊羹」と「砂糖羊羹」の項目があり、羊羹は豆と黒砂糖をこねてつくったもの、砂糖羊羹は豆と砂糖でつくる板菓子であることが記されている。ここでの「豆」は小豆のことだろう。
「小豆と小麦粉などを使った生地をこねて、かたちをつくっていた製法が次第に簡略化し、現在の蒸羊羹のような棹状のものが主流になっていったのではないかと考えられます」。
江戸時代の絵図に描かれている羊羹には四角以外のものがある。虎屋の元禄8年(1695年)の菓子見本帳(現在の商品カタログに相当するもの)を見ると、洲浜(すはま。浜辺の入り組んださまを模した意匠)形で描かれているのがわかる。

「ここに描かれているのは、古い製法を引き継いだ、かたちをつくるタイプの羊羹だと思われます。実は現在販売している虎屋の生菓子のなかにもその流れを汲んだものがあります。『羊羹製』(一般には「こなし」)と呼ばれる製法で、餡に小麦粉と糯米(もちごめ)を加工した粉を混ぜて蒸した生地を揉み、いろいろな形に仕上げます」。

1700年代には水羊羹の記述がみられるが、当初は、水分を多くして柔らかくつくった羊羹を、水羊羹といったようだ。一方、寒天をつかって固めた水羊羹も出てくる。
「虎屋には『水羊羹製』と呼んでいる生菓子の製法があって、餡に砂糖と葛粉を混ぜて煉り、蒸した生地を成形したものなのですが、こちらが古いタイプの水羊羹の流れを汲んでいるのではないかと考えています」。
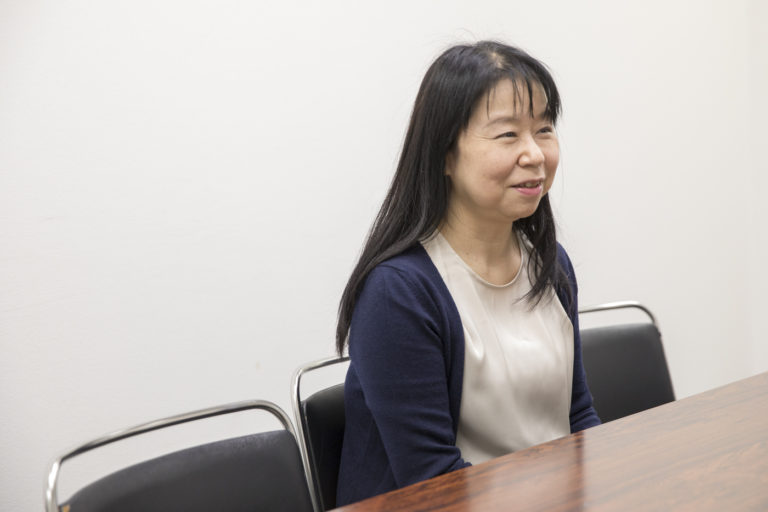
現在、羊羹の主流となっている煉羊羹が登場するのは18世紀後半といわれている。餡に寒天を加え、よく煉ってつくったもので、なめらかで弾力のある食感と、日持ちするという点が特長。煉羊羹は、江戸で人気を博し数十年のうちに地方に広まっていった。
「江戸から広まった煉羊羹ですが、当時京都で商いをしていた虎屋でつくっていたのは主に蒸羊羹で、煉羊羹の名が記録に見られるようになるのは、幕末になってからでした」。
地域や季節によって変わるさまざまな羊羹
現在、「羊羹」とよばれるものは、材料や形状、製法も様々だ。羊羹の定義はあるのだろうか。
「原材料や作り方の違いもあり定義するのは難しいのですが、おおむね小豆と砂糖を固めてつくったものとは言えるでしょうか」。

様々な材料を使用した羊羹が各地に存在するが、大きな契機となったのは明治時代の産業振興といえる。
鉄道開通など交通網の発達により観光客が増えたことで、土産物需要が高まった。また、内国勧業博覧会が開催され、政府から地元の名物を使った特産品づくりが推奨されたことも、地方色豊かな羊羹が誕生することにつながった。
「神社仏閣や名所旧跡などがある観光地では、地方色豊かな羊羹がつくられました。日持ちがし、持ち運びに便利な羊羹は旅行者にも人気だったそうです。明治~昭和の古い商標を見ると、『奈良名物大仏栗羊羹』や『成田名物栗羊羹』(千葉県)といった地名を冠したもの、柿やいちご、せりやわさびなど特産品をつかったものなどがあったことがわかります」。

四季折々の意匠の羊羹もある。虎屋では、3月に桜のモチーフ、4月に藤のモチーフといったように、季節の移ろいを感じさせる羊羹が販売されている。
「虎屋の大正7年(1918年)の菓子見本帳には470もの羊羹を含む棹菓子の意匠が掲載されています。100年以上も前の史料ですが、今も菓子づくりや、販売の際の参考につかわれているんですよ」。
ところで、一般的に夏の食べ物とされている水羊羹だが、福井県など一部の地域では冬に食べる習慣があるという。
冬の寒さは水羊羹を固めるとともに、保存にも適していたという。

現代の人々の感性に合わせた羊羹も次々と誕生している。
「各地の菓子店では、チョコレートやドライフルーツ、ナッツといった材料をつかった羊羹や、ピアノの鍵盤を模したもの、切っていくごとに意匠が変化していくものなど多種多様な羊羹がつくられています」。
中国の羊の汁物からお菓子へ。日本に伝わり、風土や文化に育まれるなかでさまざまな形で受け継がれてきた羊羹。伝統的なものから新しい形まで、これからもさまざまな羊羹が楽しめるのだろう。
参考文献:虎屋文庫『ようかん』新潮社、2019年/「虎屋文庫の羊羹・YOKAN」展小冊子、虎屋、2019年




