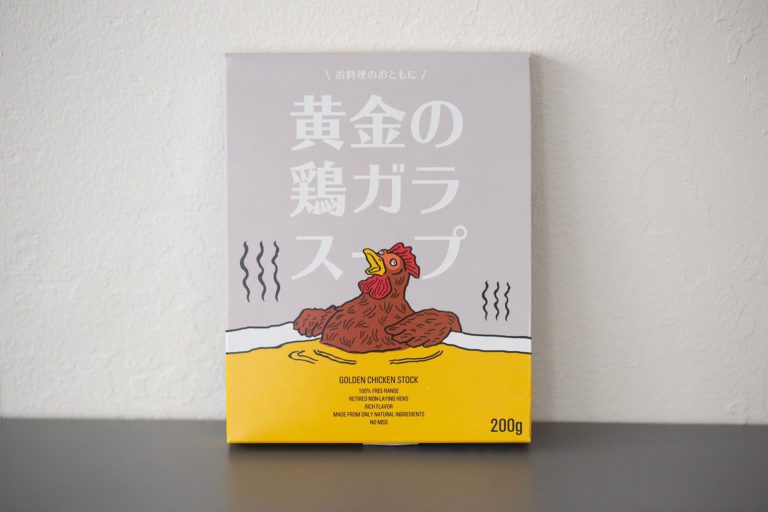白くて丸い縁起物。年神様が宿る「鏡餅」

「鏡餅」は新年の幸せをもたらす年神様が宿る場所
鏡餅の起源は平安時代、宮中でお正月に行われていた「歯固めの儀式」だと言われている。新年の長寿と健康を祈願して、硬い餅などを食べる儀式だ。もともとお正月は、新しい年の五穀豊穣や無病息災を祈る行事。鏡餅は一年の幸運を司る年神様が宿る依代(よりしろ)として準備するもので、各家で年を越す前に飾る。

「鏡餅をつくる餅つきは、年の終わりの大仕事。末広がりの“8”が入っている12月28日や、30日につくことが多かったようです。29日は苦餅、31日は一夜餅といって、あまり縁起が良くない日とされました」と、清さん。ちなみに鏡餅を飾る日も28日が多く、大掃除が済んだ清らかな家であればなお良し。また昔は、家中の神様が宿るところすべてに鏡餅を供えるのが習わしで、一番立派な鏡餅を床の間に、小さいものを台所やトイレ、玄関にも供えていたそうだ

鏡餅はその丸い形と、鏡を冠した名前に意味がある。そもそも餅は神聖な食べ物で、奈良時代に編纂された『豊後国風土記』には、丸い餅を弓で射ったところ、白い鳥になって飛び去り、その後国が荒れてしまったという伝説がある。白くて丸い餅は豊かさの象徴であり、神様の宿る特別な力があるもの。それと同時に、人々の憧れであり、尊いものだったのだ。
「現代では手軽に食べられますが、貴重な米にさらにひと手間をかけて仕上げる餅はご馳走でした。お祝いや神事には欠かせないお供え物であり、特別なものだったんです」。

飾り方はさまざまだが、スタンダードは大小2つの丸餅を重ね、てっぺんに橙と呼ばれる柑橘を乗せる形。土台は三方(さんぼう)と呼ばれる木製の台で、紅白の四方紅(しほうべに)と紙垂(しで)、裏白(うらじろ)という葉を餅の下に敷く。橙は代々家が続くように、裏白の葉は葉裏の白さから清浄な心、左右対称さから夫婦円満などを意味。四方紅と紙垂は邪悪なものを追い払う。地方や家によってはさらに縁起物として、昆布や串柿が足される場合もある。
年神様の力を身体に取り込む「鏡開き」
鏡餅は供えるだけではなく、“食べる”ということが重要だと清さん。年神様が家におられる松の内という期間が終わったら「鏡開き」を行い、大きな鏡餅をみんなで分けていただくことで、餅に宿った年神様のパワーを身体に取り込むのだ。

「鏡開き」の名前の由来は、縁起を担いでのこと。武家社会では「切る」「割る」という言葉は切腹をイメージさせるため、縁起の良い「開く」という言葉を使うようになったとされている。
鏡開きの日取りに明確な決まりはないが、関東を中心に1月11日の地域が多いようだ。かつては20日だったが、江戸幕府の第3代将軍・徳川家光が4月20日に亡くなった後、月命日を避ける意味から11日になったという説がある。また関西では15日が主流で、京都の一部では三が日明けすぐの4日に行われることもある。
「武家では具足開き、商売をする家では蔵開きなどとも呼び、お正月が終わり仕事始めのタイミングに合わせて鏡開きを行う場合も多くありました。人々の生活によっても時期が違っていたようです。鏡餅を水に浸けて保存し、『水餅』にして6月頃に食べる家や、正月飾りなどを集めて火で炊き上げる『とんど』の火で焼いて食べる地域もあります」。

お下がりの鏡餅は、邪気を払うと言われる小豆といっしょにお汁粉にしていただくのが一般的。ちなみに、「汁粉」はこし餡、関西ではつぶ餡を「ぜんざい」、関東では「田舎汁粉」などと呼ぶ。砂糖も当時は贅沢品。縁起の良い餅と砂糖をあわせた季節ならではの甘味は、新年の楽しみだったのだろう。
新しい年に感謝し、幸運を祈りながら鏡餅を食べる

鏡餅以外にも、小正月を中心に色とりどりの小さな餅を木の枝につけた「餅花」を飾る風習がある。無事に米が実ったお祝いと感謝を、餅という形に変えて神様にお供えし、「今年も豊作に違いない」と確信してあらかじめお祝いする「予祝」の意味がある。
「昔の人はたっぷりと時間をかけてお正月の準備をし新年をお祝いしましたが、その中心にあるものが餅でした。今では子どもたちにお金を贈るようになったお年玉も、そもそもは年神様からの「御魂分け」として丸餅をいただき新年の活力を得るものでした。当時の人々にとって餅を食べるという特別感は、我々とは比べ物にならないものでしょう」と、清さん。
現代では餅つきや鏡餅を作る機会は減ってしまったが、お正月には感謝と祈りを込めて鏡餅を供え、ぜひ大切な人と食べてほしい。